
テレビや新聞などのニュースを見ると
-
○○テック
-
AI(エーアイ)
などの横文字がたくさんでてきます。
このような横文字で表現される物事はうつり変わりがはげしく、数年たてば誰も使わなくなったりすることもよくあります。
しかし、時代は確実に変化していて
「Fintech(フィンテック)」
などは利用者の見えないところで徐々に浸透しつつあります。
フィンテックは銀行を代表とする金融業界に変化をもたらしました。
ここで紹介する
「InsurTech(インシュアテック)」
は保険業界版のフィンテックとも言えます。
インシュテックは保険業界を変えると期待されています。
保険加入者にとってはメリットの大きい変化ですので、どのような変化が起きているのか知っておくことは大事です。
この記事ではざっくりと
-
InsurTech(インシュアテック)とは何か?
-
保険の加入者にとってどんなメリットがあるかの
-
どんな種類の保険や事例があるのか
などについて解説したいと思います。
このページの目次
InsurTech(インシュアテック)(インシュアテック)とは?
まずは
InsurTech
の意味から説明します。
InsurTech(インシュアテック)とは
-
Insurance(保険)
-
Technology(技術)
このふたつの言葉を組み合わせた造語です。
Insur + Tech =InsurTechということですね。
かんたんに言えば、保険業界と最新のテクノロジーを組み合わせた新しい保険サービス、ということです。
会社によってはInsurTech(インシュアテック)ではなく
「InsTech(インステック)」[1]ちなみに第一生命が商標登録しています。
と呼んだりもしていますが、どちらも考え方は同じです。
ちなみにこの「テック」という言葉は
-
不動産テック
-
HRテック(人材テック)
-
Ed-tech(教育テック)
-
med-tech(医療テック)
など、さまざまな業界にも広がっています。
ただ、使う側としては特に意識しないで「便利になったな」「新しい機能だな」程度でいいと思います。
流行り物でもあるので、なんかすごそうだけど中身はまったく新しくない、なんてこともよくあります。
だから特に気にする必要はありません。
海外では2015年くらいから活性化
インシュアテックはフィンテックと比べると、テレビ等マスメディアなどでピックアップされる機会はまだ少ないです。
しかし、海外とくに欧米では2015年あたりから注目されている分野でした。
日本でも大手保険会社や損保などが取り組んでいますので、2019年以降にインシュアテックと代表格と言えるようなサービスが誕生するかもしれません。
余談ですが、あのソフトバンクは2017年にアメリカのインシュアテック「Lemonade」に出資しています。
もしかしたら海外から連れてくる黒船のような形で日本の保険市場を狙ってくるかもしれません。
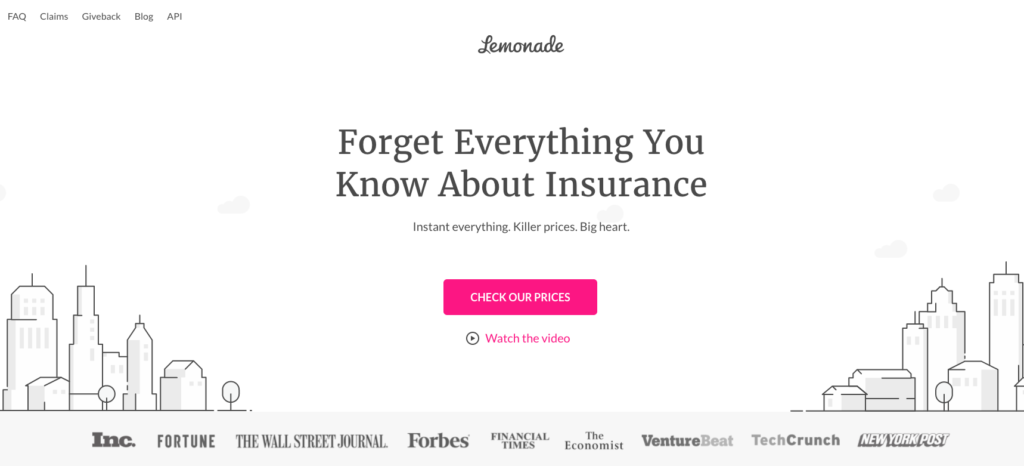
Lemonade(レモネード)
保険加入者にはどんなメリットがあるのか
ではインシュアテックと呼ばれる保険サービスは加入者にはどんなメリットがあるのでしょうか。
もちろん個別の保険によって違いはありますが、
-
スマホから1日単位で保険に加入できる
-
これまで様々な理由で保険への加入を断られていた人でも加入できる
-
保険の加入の審査が簡単になる
-
従来の保険より保険料が安くなる
-
健康に気をつけるなど自分の努力によって保険料が安くなる
-
保険の請求手続きが簡単になる
-
支払うお金と返ってくるお金が明確
-
無数にある保険商品の中から自分に合うものがすぐにわかる
など、加入者にとってはありがたいサービスが多いです。
これまでの印象だと
-
保険加入時は営業にしつこく勧誘される
-
保険に入ったらむこう数十年間おなじ保険料を払い続ける
などのあまり良くないイメージが保険業界にはありました。
インシュアテックによってこのような過去のイメージが払拭され、
-
保険への加入が必要な人だけが
-
保険加入が必要な期間だけ入る
というように「保険の当たり前」が変化する可能性があります。

Insurtechで活用されるIT・ネットの技術
Insurtechは
保険業界と最新のテクノロジーを組み合わせた新しい保険サービス
だとすでに説明しました。
ではどのようなテクノロジーが活用されているのでしょうか。
主にはITやインターネットの技術を活用していますが、メインは
-
ビッグデータ
-
Iot
-
AI(人工知能)
この3つです。
将来的にはこれに
「ブロックチェーン」
も追加されると思います。
それぞれどんなふうに活用されているかを簡単に説明します。
ビッグデータ × 保険
そもそも保険業界はデータ産業でもあります。
保険会社は病気や天変地異などの最新のデータをつねに取得して、適切な保険料を算出していました[2]保険業界にはデータを専門的に扱う「アクチュアリー(保険数理士)」という職業もあります。。
そして、インシュアテックでは社会全体のデータだけでなく、保険加入者個人のデータもおおいに活用します。
デジタル化が進んだ現在は
-
健康診断のデータ
-
人間ドックのデータ
-
個人の生活習慣に関するデータ
などの個人の健康情報のデータを集めることができます。
そして、データをもとに保険加入者がもつリスクを分析し、加入者に対して適切な保険を提案することができるのです。
将来的には究極の個人情報とも呼ばれる遺伝子の情報などを使い保険料を算出する時代が到来するかもしれません。
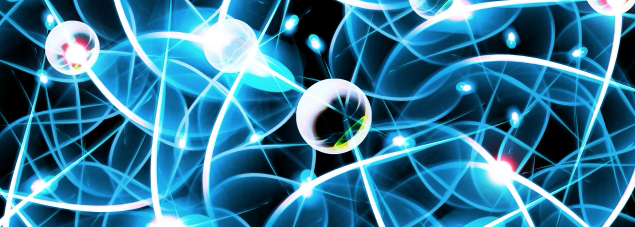
Iot × 保険
Iotは
Internet of Thing(モノのインターネット)
の略語です。
身の回りにあるモノをインターネットに接続する、という意味で使われます。
Iotを使うと時計や靴などに専用機器を仕込み、そこから個人のデータを取得することができるようになります。
つまり、Iotが進むにつれて保険のプランニングに必要なデータを現在より大量に取得できるようになる、ということです。
Iotは保険のビッグデータ化をうながす仕組みでもあります。
AI(人工知能) × 保険
AI(人工知能)は保険業界にも導入されています。
加入者側の目線だと
-
保険の外交員(営業窓口)がAIによるチャットボットになる[3]チャットボットとはLINEのような会話形式でやりとりしてくれるネット上のプログラムのことです
-
保険金の支払い時の査定で使われる
-
自分が希望する内容にもっとも近い保険をAIが提案してくれる
などに人工知能が使われます。
具体的には保険会社側の作業を人工知能が行うことにより、加入者の時間的な手間や書類作成の負担が減ります。
人工知能はたくさんのデータを教師データ[4]参考にするデータのこととして使うことによって精度が高くなります。
なので大量のデータをあつかう保険業界とは相性がとても良いのです。
自分に合った保険商品を提案してくれるAIは
「ロボアド(ロボットアドバイザー)」
と呼ばれており、将来的には今ある保険の代理店を駆逐する存在になるかもしれません。

Insurtechによって生まれる新しい種類の保険
Insurtechの代表的な技術である
-
ビッグデータ
-
Iot
-
AI(人工知能)
などをベースにして新しいタイプの保険がぞくぞくと生まれています。
代表的な保険は
-
テレマティクス保険
-
ウェアラブル端末を使った保険
-
P2P保険
-
マイクロ保険
-
オンデマンド保険
などです。
こちらも保険の種類ごと個別に簡単に解説したいと思います。
その1. テレマティクス保険
テレマティクス保険の
「テレマティクス」
とは
-
テレコミュニケーション
-
インフォマティクス
を組み合わせた造語です。
おもに自動車保険として使われている保険で、車の中に
-
専用アプリをインストールしたスマートフォン
-
専用の部品
などを入れて、運転のデータを取得します。
そして、安全運転をしている人ほど保険料が割引されます。
この仕組みによって保険加入者である自動車の運転手は
-
安全運転に気をつけるようになる
-
安全運転した結果として保険料が安くなる
などのメリットがあります。
テレマティクス保険については日本では2015年にソニー損保によって実用化されています。
他にも損保ジャパンのテレマティクス保険が人気のようです。

その2. ウェアラブル端末を使った保険
ウェアラブル端末を使った保険では、加入者が時計などのウェアラブル端末を装着します。
そして、加入者が健康的に活動しているかどうかを端末が測定します。
もし健康的な生活をしているのなら[5]例としてはウォーキングやランニングです。、保険料は安くなります。
健康的な生活習慣を身につけて加入者が健康になれば保険金の請求が減るので、保険会社にとってもメリットがあります。
このような個人データは
「ライフログ」
と呼ばれ、保険以外の分野でも活用されています。
その3. マイクロ保険
マイクロ保険は
-
少額の保険料で加入できるけど
-
保障する範囲は狭い
という保険です。
保険に加入したいけど、毎月の保険料を払うのが嫌だと感じている人に向いています。
発展途上国で目立つ保険でもあります。
マイクロ保険はすぐ後に紹介するオンデマンド保険とかぶる部分があります。
なのでどちらも同じだ、くらいに考えてよいかもしれません。
その4. オンデマンド保険
オンデマンド保険は、入りたいその時に入れる保険、という意味です。
つまりは、
-
スマートフォンや搭載されているアプリを使い
-
入りたい時にすぐ入れる
という保険です。
例えば家財保険に入りたいとき、オンデマンド型の保険を使えば保険に加入したい家財を撮影し、それを保険会社に送信するだけですぐに保険に加入ができます。
そして保険金の請求や審査もスマホからできます。
わざわざ保険会社に行ったり外交員に会ったりすることを面倒だと感じる若者向けの保険ですね。
その5. P2P保険
P2P保険とは、友達でグループを作り保険に加入できる仕組みの保険です。
たくさんの友達と一緒に保険に入れば保険料が割安になります[6]リアルな世界の友達である必要はありません。。
滅多に起きないであろうリスクを友達同士で分散して保険料をシェアする、ということですね。
ここでは詳しく説明しませんが、P2P保険には行動経済学の要素をサービスに導入している会社が多いです。
海外のInsurtechの事例となるサービス
ここからは実際にインシュアテックの事例となるサービスを紹介していきます。
まずは海外企業のサービスからです。
P2P保険のLemonade(レモネード)
インシュアテックの代表的な企業がP2P保険を提供しているLemonade(レモネード)です。
基本的にはスマホから加入できる家財保険ですが
-
友達プール
-
寄付による社会貢献
-
手数料は一律で20%
などの仕組みを導入したりして保険会社としての透明化に成功しています。
Lemonade(レモネード)の仕組みなどについては下記リンク先で確認してください。
チャットボットが最適な保険を提案してくれるSure
Lemonadeは自社で保険を提供していますが、保険の仲介に徹するインシュアテック企業もあります。
そのうちのひとつがアメリカの
「Sure」
です。
Sureはスマホアプリからチャットボットで希望する保険内容を入力すると最適の保険を提案してくれます。
保険の対象は
-
かばん
-
趣味のコレクション
-
美術品
-
宝石や時計
-
レンタカー
-
スマートフォン
などです。
仲介に徹することによって
-
加入者に最適なUX/UI
-
保険提案のアルゴリズム
などの開発に注力できる、というメリットがあるようです。
・Sure公式サイト
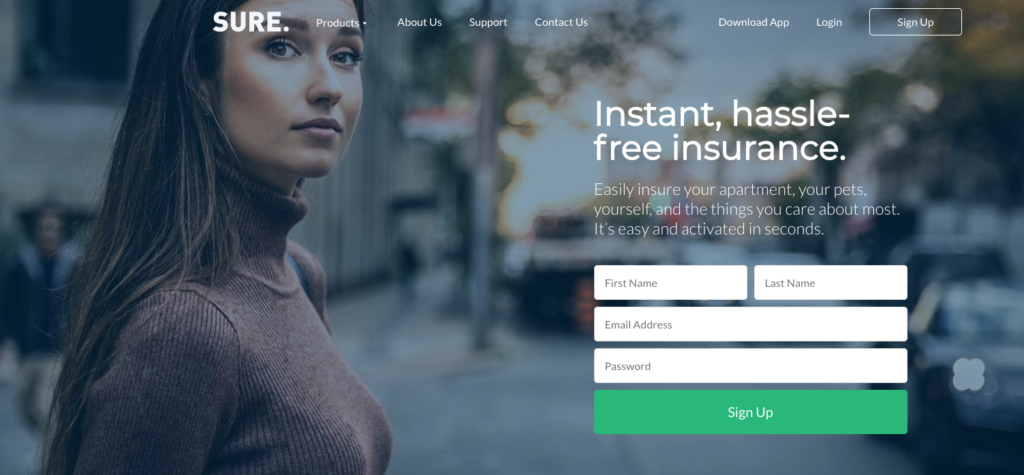
オンデマンド保険のTrov
Trov(トロブ)はオンデマンド型の保険です。
基本的にはスマホアプリで加入から保険金請求まですべて完結します。
保険対象は家電・家財などがメインですが、googleの傘下企業と提携して自動運転車も保険対象にしています。
日本のSOMPOホールディングスと資本提携をしていますので、日本への進出も期待できます。
・Trov公式サイト
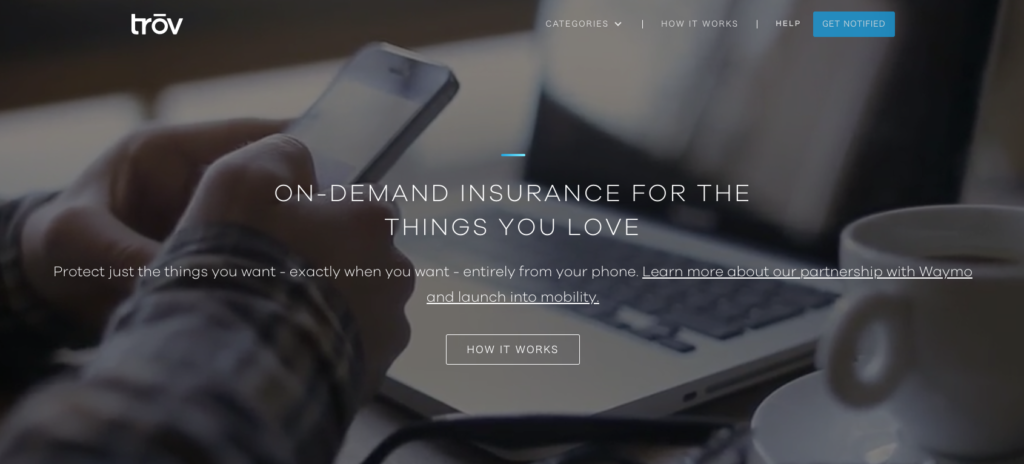
日本のInsurtechの事例となるサービス
続いて日本のインシュアテックの事例となるサービスを紹介していきます。
P2P保険のjustInCase(ジャストインケース)
justInCase(ジャストインケース)は
-
P2P保険
-
オンデマンド保険
-
マイクロ保険
の要素が取り入れられた保険サービスです。
当面はスマートフォンの画面ガラス破損に特化するサービスとなります。
詳しくはリンク先で確認してください。
1日あたりで家電保険に入れる「Warrantee Now(ワランティナウ)」
Warrantee Now(ワランティナウ)は1日単位で家電を保険に加入させることができるサービスです。
もちろんスマートフォンからの操作で完結します。
ただ、一般的な家電保険とは異なりWarrantee Nowは修理代を出してくれる保険ですので注意してください。
こちらも詳しくはリンク先をチェックしてください。
ロボットアドバイザーのDonuts(ドーナッツ)
投資に続いて、保険でのロボットアドバイザーが登場しています。
保険のロボットアドバイザーは
-
加入希望者にいくつか質問をして
-
質問の回答をAI(人工知能)が分析し、最適な保険を提案する
という仕組みです。
日本では「Donuts(ドーナッツ)」という保険のロボットアドバイザーが2018年にサービスの提供を開始しています。











